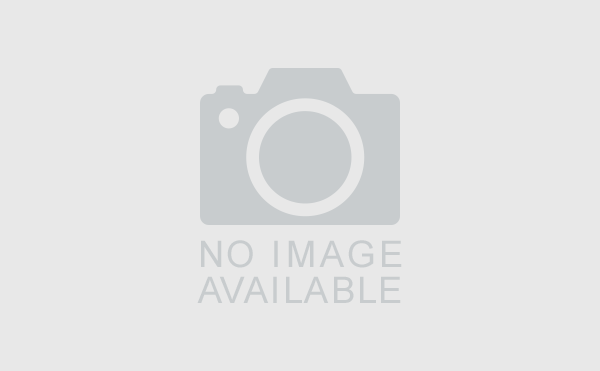青色申告の書類作成は確定申告コーナーで
目次
青色申告は毎年2/15スタート
こんにちは、こたかです。
毎年2/15から確定申告の受付が始まりますが、青色申告を選択している個人事業主は申告の書類の提出準備を行う時期だったりします。
事業を始めたときの最初の申告では、書類の作成に戸惑う事もあります。
青色申告は事業の決算、確定申告は個人の決算
おおざっぱに言うと、青色申告/白色申告は事業の収支の申告、確定申告は個人の収支の申告となっています。
事業の収支の報告については、以下の三種から選択しますが、青色申告については、事前に税務署へ事業の登録が必要になります。
- 白色申告(簡易簿記)
- 青色申告(簡易簿記)
- 青色申告(複式簿記)
こたかは「青色申告の複式簿記」選択しています。
確定申告コーナーで書類作成
簿記の収支情報をもとに、青色申告の書類を作成します。
「損益計算書」と「貸借対照表」の2つが作れれば、税務署のサイト「確定申告コーナー」で申告書類を作成することができます。
税務署へ開業登録を行っていると、1月頃に「確定申告コーナー」で紐づけすることができる「整理番号」がはがきで送られてきます。
はがきを開封して右側のヘッダー部分に小さく番号が書かれています。2つの番号が「-」で区切られていて。右側が整理番号です。
最初に青白申告の作成、次に確定申告の作成の流れになります。
確定申告では、社会保険の控除(国民年金保険・国民健康保険※両方とも保険呼ばわりされていて紛らわし)、
地震保険の控除、医療費控除については医療費が10万円を超えたときにだけ、超えた分が所得から控除されます。
医療費控除額は上限もあり、よほど医療費を使い、かつ業績が良くないと還元額は少額になります。
こたかは、歯医者と耳鼻科に年2回も行かないので、医療費控除は無縁です。
一度だけ医療費控除を申請したことがありましたが、医療費と薬の明細書の集計で大変な事務作業を行った割に1000円も返ってこなかった気がします。
それ以降、作業の方が無駄なので申請していません。
控除は控除申請を省略して税金控除を辞退することを選択できます。
ただし、配偶者控除だけは住民税とリンクしているので省略せず、配偶者の収入が「0円」なのか、課税象額以上なら源泉徴収書を記入する必要があります。
収益に対応する正しい税金を納めていれば、控除を省略して、控除なしで税金を多く払っても良いわけです。
確定申告の時に青色申告をセットで提出
作成した「青色申告」と「確定申告」の書類はセットで提出します。
個人事業は収支が個人に紐づくので、法人である「会社」とは異なります。
「確定申告」では個人の収支を申告し、事業の収支はさらに詳しく「青色申告」で申告するといった具合です。
そのため「確定申告」には事業の詳細は記載せず事業所得だけ記入し、事業の損益は青色申告に記載します。
銀行振り込みで対応しているのは確定申告のみ。贈与税は非対応!
確定申告の納税は銀行引き落としにも対応しています。事前に口座の申請をしておけば自動引き落とししてくれます。
同じ時期の申告に「贈与税」があり、すぐ隣で受け付けていることがあります。
贈与税の納付は銀行に行って振込用紙で振り込むことが原則です。
贈与税は銀行引き落としに対応していません。何故か受付の職員は「銀行引き落としが便利です!」と勧めしてきます。
ここで勘違いしないようにご注意ください。
なんども言いますが贈与税は引き落としされることはありません。
贈与税には予告なく3/15までで期限切れになるため放置すると延滞料金を請求されます。
一日単位で加算させるので、土日が挟まると残念なことになります。税務署が休みなので納税できないためです。
税務署の増税戦略と思っておいた方が良いでしょう。
贈与税を払うような人にはコンビニ払いの上限は低いため、銀行振り込みの一択になります。
銀行を利用する際には銀行の面会予約と印鑑と通帳を忘れずにどうぞ。
まとめ
今日は確定申告についての記事でした。
個人事業をはじめたばかりの人は、税務の情報収集にも忙しいと思います。
今はネットで調べることができますが、税務については制度の見直しも頻繁にあるので追従するのにも苦労します。
税務にも「車輪の再発明」がなくなるように情報共有が進むと良いですね!
それではまた次の記事でお会いしましょう。